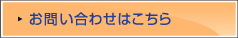各部門のご紹介|苫小牧日翔病院
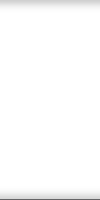
採用情報|一緒に皆様の力になりましょう
院内託児所|ピッコロ保育園
臨床工学科

臨床工学技士とは
病院で使用する医療機器を取り扱う専門家
医師の指示のもと生命維持装置(人工透析装置や人工呼吸器など)を安全かつ的確に操作し、病院で取り扱う医療機器の保守・点検をおこなっています。
自身のスキルアップのため学会や勉強会に参加し、各種認定資格の取得も目指しています。
医師や看護師などと連携し医療現場を支える存在
チーム医療では患者さんを中心に多くのスタッフが連携して医療をおこないます。
臨床工学技士は医療機器の管理に携わるだけでなく、患者さんとも直接関わりコミュニケーションをとることで治療を円滑におこなえるよう努めています。
臨床工学科 科長
臨床工学科には院内でCE(Clinical Engineer)と呼ばれている臨床工学技士が所属しています。臨床工学技士とは、医学的知識と工学的知識を兼ね備えた医療機器の専門家です。
医療現場には様々な治療用医療機器、生命維持装置が導入されており、当院においても臨床工学科がこれらの操作・保守管理を中心に業務対応しています。現在の医療現場では高度化した医療機器が数多く使用されており、それら医療機器の安全性と信頼性の確保に加え病院経営を考慮した計画的な管理は、医療機器の専門家である臨床工学技士の重要な役割となっています。
臨床工学科長 佐藤 光人
主な業務
-

人工透析業務
-

VAIVT業務
-

心臓カテーテル検査業務
-

人工呼吸器業務
-

高気圧酸素業務
-

医療機器管理業務
-

内視鏡業務
人工透析業務
-
人工透析とは腎臓の機能が正常に働かなくなった際に、人工透析装置を使用し排泄・代謝をおこなう治療です。
臨床工学技士は透析器材の準備・透析液の作製・プライミング・穿刺・開始操作・治療中の患者モニターの監視・返血操作をはじめ、安全に透析がおこなえるよう装置の定期点検や、水質管理をおこなっています。
その他にグラフト管理・生体計測(SPP測定)・CTR測定や災害対策・リスクマネージメントにも力を入れています。 -

-
VAIVT業務
VAIVTとは人工透析をおこなう際に穿刺部位として用いられるバスキュラーアクセス(VA)に狭窄などのトラブルが見られた際におこなわれる治療です。
当院では経皮的に血管内にバルーンカテーテルを挿入し狭窄部位を拡張する
経皮的血管形成術(PTA)を中心に、血栓除去・血栓吸引などの治療をおこなっており、臨床工学技士は清潔野介助や使用物品の管理・電子台帳による治療記録の管理などをおこなっています。 -


心臓カテーテル検査業務
心臓カテーテル検査では、経皮的に血管内にカテーテルを挿入し、心臓の筋肉に血液を供給している冠動脈に造影剤を注入し、X線で撮影する検査(冠動脈造影:CAG)をおこないます。検査で血管の狭窄などを発見した際にはバルーンやステントと呼ばれるデバイスを用いて血管を広げる治療(経皮的冠動脈形成術:PCI)をおこないます。
当院ではその他に、末梢動脈カテーテル治療(EVT)・ペースメーカー植え込み・薬物負荷試験・電気生理学的検査・下大静脈(IVC)フィルター留置抜去など様々な治療検査をおこなっています。
臨床工学技士は清潔野介助業務、患者監視装置(ポリグラフ)・補助循環装置(IABP)や画像診断装置(IVUS)など関連装置の操作・保守・管理などをおこなっています。
人工呼吸器業務
-
肺の機能が低下し呼吸が十分にできなくなった患者さんには呼吸を代行する人工呼吸器が装着されます。
使用中の呼吸器に異常がないか1日2回の点検をおこない、稼働していない呼吸器はいつでも貸出できるように定期点検をして管理しています。 -

高気圧酸素療法
-
高い気圧の環境下で酸素を吸入させることで、血液中の酸素を増やすのが高気圧酸素療法です。
脳梗塞や腸閉塞、一酸化炭素中毒などの治療に用いられます。
当院では第1種装置を2台使用しており、治療開始前の点検・操作・使用後点検をおこなっています。
10~15分かけて装置内の気圧を大気圧の倍にあたる2気圧まで高め、約60分間の治療をおこない10~15分かけて減圧をします。
治療中は装置に備え付けのマイクでいつでも会話ができます。 -

医療機器管理業務
医療機器の修理、定期点検、病棟・外来での医療機器のトラブル対応、機器の貸出・返却・所在把握、院内スタッフに対する医療機器の操作安全講習、マニュアルの作成など院内の医療機器に関連する様々な業務をおこなっています。
その他に除細動器・AED・麻酔器・血液ガス分析装置・医療ガス設備の日常点検・定期点検にも携わっています。
内視鏡業務
-
内視鏡検査とは先端に小型カメラを内蔵した細長い管を口または肛門から挿入し、食道・胃・十二指腸や大腸などの消化管の内部を観察する検査です。
当院では検査で発見した出血部位の止血(内視鏡的止血術)やポリープの切除などの処置、内視鏡を使って胆管・膵管を観察するための造影検査ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)などもおこなっており、臨床工学技士は検査介助や処置具の操作、使用機器の日常点検や洗浄業務をおこなっています。 -